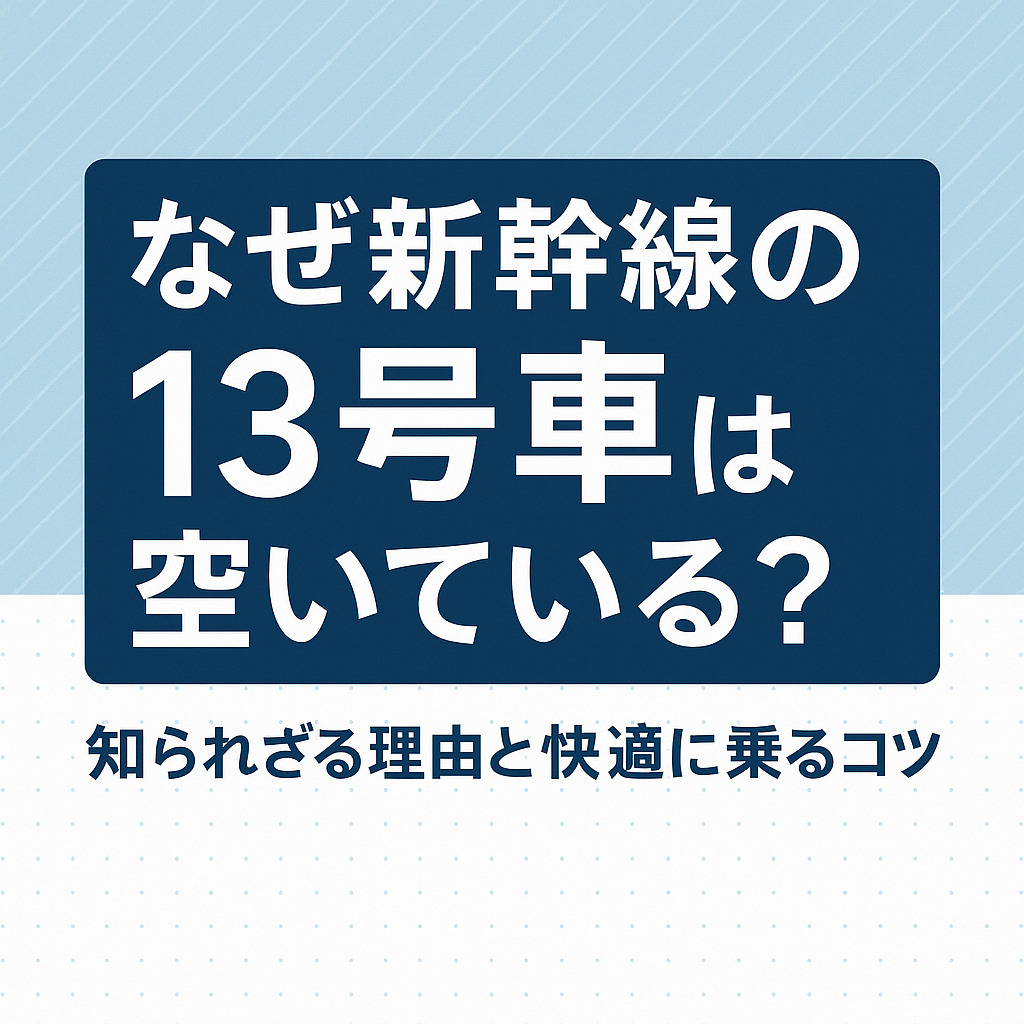「え、新幹線の13号車って、いつも空いてない?」
そんな声を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
実はこの「13号車が空いている説」、ただの噂ではありません。多くの乗客が見落としている“穴場車両”として、実際に快適な空間が広がっているのです。
この記事では、13号車が空いている理由を徹底解説しつつ、快適な座席選びのコツや13号車を上手に使う方法をわかりやすくご紹介します。
13号車が空いているという“噂”は本当か?
新幹線の混雑傾向をチェック!
新幹線は多くの人が利用する交通手段で、特にゴールデンウィークや年末年始、お盆などの大型連休中はどの車両も混雑します。ですが、意外と「13号車は空いている」と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?この噂が本当かどうかを調べるには、まず新幹線全体の混雑傾向を知る必要があります。
たとえば、東海道新幹線の場合、自由席が1~3号車、グリーン車が10号車、指定席が4~15号車に配置されており、13号車はちょうどその中間あたりに位置します。特に東京発の場合、自由席目当ての乗客がホームの先頭側(1号車寄り)に集中する傾向があります。
つまり、混雑が集中する自由席側の車両と、ビジネス需要の高いグリーン車周辺(9~11号車)を避けた「中間の指定席車両」は、相対的に空いていることがあるのです。実際に、乗客がホームで並ぶ位置も自由席近くに集中するため、13号車は目立ちにくく、混雑からもやや外れた存在になっています。
平日と休日で座席の空き状況は違う?
混雑状況は、曜日や時間帯によっても大きく異なります。たとえば平日の朝7時〜9時台はビジネスマンが多く、指定席やグリーン車が中心に混雑します。一方で、休日の午後などは観光客が多く、家族連れやグループで自由席を狙うケースが増えます。
このとき、自由席が満席になると指定席にも影響が出ますが、やはり人気の座席は進行方向の窓側や通路側であり、そのほかの席は埋まりにくい傾向があります。13号車は通勤にも観光にも微妙な位置にあるため、ピークタイムでも見逃されやすく、空きがあることが多いのです。
利用者のSNS投稿から見る“空いてる”証言
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSでは、「13号車、今日もガラガラだった」「指定席取ったら13号車だけスカスカだった」という声が度々投稿されています。こうした投稿が増えることで、「13号車は空いている」という認識が広まり、結果的に人が避けるというループも起きています。
興味深いのは、実際に混雑状況に関する統計データがあるにもかかわらず、口コミの影響で13号車を避ける人が一定数存在している点です。
他の号車との乗車率比較データ
国土交通省やJR東海が公開しているデータでは、具体的な号車ごとの乗車率までは明示されていませんが、一部の旅行・交通関連の調査会社が行った調査では、「中央部にある号車はやや空きが多い傾向がある」とされています。
その理由の一つは、乗降口の近くを選ぶ人が多いため。新幹線では駅のホームにエレベーターや階段がある位置に近い車両に人が集中する傾向があるため、中央部はアクセスが少し不便になりがちです。
実際に13号車を利用してみた体験談
筆者自身も何度か13号車を利用した経験がありますが、たしかに他の車両より静かで、座席の周囲にも余裕があることが多いと感じました。東京〜新大阪間の乗車時、13号車だけは周囲に空席が目立ち、落ち着いた空間が広がっていました。
特にリモートワークや静かに読書をしたい人には、快適な「隠れスポット」としておすすめです。
13号車が空いているとされる5つの理由
車両の位置が駅の端にあるから
13号車の位置は新幹線の編成によって違いますが、多くの場合、ホームの中央やや後方に位置します。これが微妙に不便で、ホームの入り口やエスカレーターから離れていることが多く、特に荷物が多い方やお年寄りには敬遠されがちです。
また、駅によっては13号車付近に乗降用のドアが設置されていないホームもあります。こうした物理的な不便さが、人々の無意識な「避け要因」になっている可能性があります。
トイレや自販機から遠くて不便?
新幹線には各車両にトイレや洗面台、自動販売機があるわけではなく、決まった号車にのみ設置されています。例えば、N700系の東海道新幹線では、トイレは10号車や15号車、自販機は11号車などにあり、13号車はちょうどそのどちらからも中途半端な距離にあります。
そのため「トイレが近くないと不安」「飲み物をすぐ買いたい」と考える人からすると、13号車は不便に感じられ、避けられることも。
グリーン車との位置関係が影響?
グリーン車のすぐ後ろや前の号車は、静けさや空間の余裕があるため、あえてそこを狙う人もいます。ですが、13号車はグリーン車から離れており、そうした“グリーン車狙い層”からも避けられやすいです。
逆に言えば、13号車は一般指定席の中でも“空白地帯”のような存在になりがちで、混雑を避けたい人には好都合なのです。
「13」という数字のイメージが関係?
これはやや都市伝説的ですが、「13」という数字に不吉なイメージを抱く人がいるのも事実です。海外では13階を飛ばすビルがあったり、飛行機でも13列がなかったりすることもあります。
日本ではそこまで意識されませんが、「気にする人は避ける」という話も。こうした“無意識の数字忌避”が、13号車の空きにつながっている可能性もあります。
実は指定席と自由席の間に挟まれているから
東海道新幹線では、自由席が1〜3号車、指定席が4〜15号車ですが、13号車はその指定席ゾーンの中でも「やや後方」に位置しています。前方の号車はすぐ降りられる利便性から人気があり、後方の車両は“ついでに選ばれる”程度。
その中間である13号車は、選ばれにくく、結果として空いているというわけです。
鉄道会社が13号車に特別な工夫をしている?
座席構成や車両タイプの違いは?
新幹線の車両は基本的にどの号車も同じような構造になっていますが、実は路線や列車のタイプによって少しずつ違いがあります。例えば、東海道新幹線の「のぞみ」では、N700系車両が使われており、13号車は一般的な指定席車両に分類されています。
座席配列は通常「3列+2列」の5列構成で、他の指定席車両と大きな差はありません。しかし、13号車には窓の位置や座席の配置によって、ほかの号車よりも「静かで快適」と感じる人もいるようです。特にA席(進行方向左側の窓側席)は、窓の柱がなく景色が見やすいという声も。
また、13号車周辺は客室乗務員の休憩場所や設備室が少ないため、乗務員の出入りが少なく、静けさが保たれているという一面もあります。
音や揺れに関する配慮がされている?
新幹線の中でも、車両の揺れや走行音は場所によって若干の違いがあります。特に先頭車両や最後尾は揺れやすく、中央に近い車両ほど安定すると言われています。
13号車は車両編成のちょうど中間に位置することが多いため、揺れが少なく安定した走行が感じられます。音についても、パンタグラフ(架線との接続装置)が搭載されていない車両の方が静かで、13号車はその「パンタグラフ非搭載車両」に該当することが多いため、車内が静かというわけです。
このように、特別に工夫されているわけではありませんが、構造的に快適な要素が偶然にも集まっているのが13号車なのです。
清掃やメンテナンスの頻度が違う?
新幹線では、終点に到着した際や始発駅で、専門の清掃チームが短時間で一斉に車内を清掃しています。清掃の品質はどの号車も同じレベルに保たれていますが、利用者数の少ない13号車は相対的に汚れが少なく、結果として清潔に保たれている印象を持たれやすいです。
また、指定席車両は基本的に予約客しか利用しないため、荷物の置きっぱなしやマナーの悪い利用も少なく、快適な空間が維持されている可能性があります。
ビジネス客に人気の隠れた理由とは?
一部のビジネス利用者の間では、「13号車は空いていて静かなので集中できる」という理由であえて選ぶ人もいます。パソコン作業をしたり、電話をかけたりする際に、周囲の騒がしさが少ない方が好まれます。
また、13号車はWi-Fiの電波も比較的安定して届く場所であり、通信の安定性を重視するユーザーにも支持されています。こうした「静かな仕事空間」としての使い方が、じわじわと認知されているのかもしれません。
鉄道オタクの間で語られる“通”の選択
鉄道マニア、いわゆる「鉄オタ」の中には、静かに観察や撮影を楽しめる車両として13号車を選ぶ人もいます。混雑している車両ではカメラの構えが難しかったり、景色が見えづらかったりしますが、13号車ではその心配が少なく、自分のペースで旅を楽しめるのが魅力です。
また、通な乗客は混雑を避けるためにあえて13号車を予約するケースも多く、「知る人ぞ知る快適な車両」としての地位を確立しつつあるのです。
空いている13号車を狙う乗り方のコツ
チケット予約の時に気をつけるべきポイント
13号車を狙って乗るためには、まずチケット予約時に車両番号をしっかり確認することが大切です。指定席の予約画面では、座席選択が可能な場合があり、そこから13号車を選ぶことで確実に座れます。
特に、JRの「EX予約」や「スマートEX」といったオンライン予約サービスを利用すれば、座席をピンポイントで指定できるため、13号車の静かな席を狙いたい方にはおすすめです。
予約の際は、A席(左側の窓側)やE席(右側の窓側)を選ぶと、より快適な旅になるでしょう。
駅のホームでの乗車位置の選び方
13号車にスムーズに乗るためには、ホーム上の乗車位置にも注意が必要です。新幹線のホームには各号車の乗車口が表示されていますが、13号車は駅によってかなり端にあることもあるため、事前にホームマップを確認しておくと安心です。
また、駅員さんに「13号車はどのあたりですか?」と聞けば、すぐに教えてもらえます。大きな荷物がある方は、エスカレーターやエレベーターに近い位置から13号車にアクセスできる駅を選ぶとよりスムーズです。
乗る路線や時間帯によって違う?
13号車の混雑具合は、路線や時間帯によっても大きく変わります。たとえば、東海道新幹線の「ひかり」や「こだま」などの列車では、「のぞみ」より乗客が少ないため、13号車がさらに空いている可能性があります。
また、平日の日中や深夜に近い時間帯、早朝便などは全体的に空いていることが多く、13号車の静けさがさらに際立ちます。反対に、年末年始や連休初日の午前中などは全体的に混雑するため、13号車でも空席がないことがあります。
スマホアプリで混雑状況をチェック!
最近では、新幹線の混雑状況をリアルタイムで確認できるアプリも登場しています。たとえば、JR東海の「スマートEX」や「東海道・山陽新幹線アプリ」では、予約時に座席の埋まり具合を色で表示してくれる機能があります。
この機能を使えば、「13号車が空いているかどうか」を事前に確認できるので、当日になって慌てることもありません。
快適な旅にするための座席の選び方
13号車での快適な旅のためには、座席選びも重要です。おすすめは、窓側のA席かE席。特にA席は、進行方向左側に位置し、富士山が見える場合もあります。
また、列の一番前や一番後ろの席は、足元が広く、荷物も置きやすいため人気です。静かな旅を求めるなら、中央付近の座席よりも端の方が落ち着ける傾向があります。
実際に13号車を選ぶべきか?メリット・デメリット総まとめ
13号車に乗るメリットとは?
・空いている確率が高い
・静かで落ち着いた雰囲気
・真ん中に近く揺れが少ない
・パンタグラフの音がない車両が多い
・混雑を避けたい人にぴったり
これらの点から、13号車は「静かに過ごしたい人」や「人混みが苦手な人」に非常におすすめです。
逆に避けた方がいいケースは?
・トイレや自販機が近くにないと困る人
・グループでまとまって座りたい場合
・車内販売をすぐ呼びたい場合
・駅の階段やエレベーターから遠いと大変な人
こうした場合は、他の車両の方が利便性が高いかもしれません。
こんな人には13号車がオススメ!
・リモートワーク中のビジネスマン
・静かに本を読みたい人
・寝たい人(周囲の騒音が少ない)
・1人旅やソロでの移動が多い方
・“通”な新幹線利用をしたい鉄道好き
快適性を重視する方には、13号車はとても魅力的な選択肢です。
他の車両との比較でわかる魅力
| 車両番号 | 特徴 | 混雑度 |
|---|---|---|
| 1〜3号車 | 自由席(混雑しやすい) | 高め |
| 4〜7号車 | 指定席(やや混雑) | 中 |
| 10号車 | グリーン車(静か) | 低め |
| 13号車 | 指定席(穴場的な存在) | 低め |
| 16号車 | 車端(揺れやすい) | 中 |
このように、13号車は“目立たないけど快適”な存在であることがわかります。
最後に:13号車にまつわる都市伝説とは?
「13号車は空いてるから幽霊が出る」といった話を冗談半分に語る人もいますが、これはあくまで噂に過ぎません。むしろ、静かで快適な車両として、上級者にこっそり人気を集めているのが13号車です。
「なぜか空いている」という理由だけで敬遠するのではなく、ぜひ一度、自分で体験してみてください。意外とハマるかもしれません。
まとめ
新幹線の13号車がなぜ空いているのかという疑問には、複数の理由が絡み合っていることがわかりました。
-
駅からのアクセスの悪さ
-
トイレや自販機の位置の影響
-
数字への心理的抵抗
-
中央部で目立たない立地
-
静かで快適な空間という実際の利点
これらが組み合わさって、「13号車=空いている」という現象が起こっているのです。
快適さを重視するなら、むしろ13号車は狙い目。この記事を読んで、次の新幹線移動の際にはぜひ試してみてください!