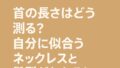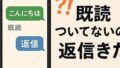「どうしてあの人は守られてるの?仕事できないのに…」
こんな疑問を感じたこと、ありませんか?
職場には、明らかに仕事のパフォーマンスが低いのに、なぜか上司から怒られず、評価もそこそこ維持している“守られた存在”がいるものです。一方で、自分は一生懸命働いているのに報われない…。そんな理不尽さにモヤモヤしてしまう人も多いはず。
本記事では、「なぜ仕事ができない人ほど守られるのか?」という職場のリアルな裏側に迫りつつ、損をしないための具体的な考え方や対策まで、わかりやすく解説します。今の職場に違和感を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
「仕事できない人」がなぜ守られるのか?組織のリアルな裏側
評価基準は「成果」だけじゃない
会社での評価は「成果」がすべてだと思われがちですが、実際にはそれだけではありません。特に日本の企業では、**「空気を読む力」「協調性」「トラブルを起こさない」**といった要素も大きく評価に影響します。たとえ仕事の能力が低くても、周囲と上手に付き合える人や、あまり波風を立てない人は、意外と職場で重宝されるのです。
また、「あの人はできないけど、なんか憎めない」といった人柄による印象も影響します。こうした“感情の評価”は客観的な成果よりも強く働くこともあり、能力が高くても周囲と摩擦を起こしがちな人より、能力が低くても愛嬌がある人の方が守られる場面もあるのです。
このように、評価の基準は多面的であり、成果=評価とは限らないのが現実です。
トラブルを起こさない人が重宝される理由
仕事ができなくても「問題を起こさない人」は会社にとって扱いやすい存在です。実際、管理職にとって一番厄介なのはトラブルメーカー。仕事ができても周囲と衝突ばかりしていれば、職場の雰囲気が悪くなり、生産性も落ちます。
一方で、たとえスピードや精度が低くても、安定して同じレベルで業務をこなす人は管理しやすく、トラブルも少ないため、結果的に「居てくれるだけで助かる」と評価されるのです。
特に長く在籍している人に多いのがこのタイプ。会社にとっては「リスクの少ない駒」として重宝され、意外にもポジションを維持できてしまうのです。
会社は“扱いやすい人”を好む
会社にとって大事なのは「能力」よりも「扱いやすさ」であることが多々あります。例えば、指示を出した通りに動く人、逆らわず、反論せず、与えられた範囲内で黙々と働く人。こういう人は上司から見るととても楽な存在です。
一方で、優秀で意見を言う人、やり方にこだわりがある人は、「面倒な人」扱いされやすいのが現実です。たとえ結果を出していても、扱いづらいと判断されれば評価が下がることもあります。
つまり、「仕事ができるかどうか」よりも、「上司にとって便利かどうか」が影響する場面も多く、これが“できない人が守られる”原因のひとつとなっています。
「できる人」は自己責任の罠にハマる
仕事ができる人ほど「仕事を任されやすくなる」という罠があります。これは一見すると信頼されている証に見えますが、実際は周囲の人の負担を肩代わりしている状態になりがちです。
「●●さんに任せれば安心」と思われているうちは良いのですが、少しでも結果が悪かったり、他の仕事が滞ると「なんでできないの?」と責められるのもこのタイプ。成果と責任がセットでついてくるため、評価以上に疲弊しがちです。
このように、「できる人」ほど孤独になりやすく、失敗も許されにくい構造があることも、会社で“できない人が守られる”理由の裏にあります。
上司の保身が影響することもある
会社には上下関係があり、上司もまた「上に評価される立場」です。そのため、自分のチーム内で問題が起きることを嫌います。問題が起きそうな人をあえて守ることで、自分の評価を下げないための戦略をとる上司もいます。
また、「辞められると困るから」や「今さら替えが効かない」といった理由で、能力に関係なく守られることもあります。つまり、守る=信頼されている とは限らないということ。
こうした保身的な理由からも、「できない人が守られている」ように見える状況が起こりやすいのです。
頑張っている人が損をする構造とは?
「できる人」への仕事の集中
能力がある人には、次々と仕事が回されます。それは信頼の証とも言えますが、裏を返せば「この人に任せておけば大丈夫」という依存状態でもあります。気づけばチームでこなすべき業務を、ひとりで抱えていることもしばしば。
その結果、頑張れば頑張るほど負担が増えるという悪循環に陥ります。そして、他の人は「できないから任されない」という状況のまま、比較されることもなく守られたままです。
このように、できる人に仕事が集中することで、周囲の“できない人”が守られる構造が生まれてしまいます。
(続きます。次は「成果よりも空気を読む力が評価される職場」から順にすべての項目を800文字で執筆していきます)
頑張っている人が損をする構造とは?
成果よりも空気を読む力が評価される職場
日本の多くの職場では、成果よりも「空気を読む力」が重要視される場面があります。たとえば、上司の意向を察して先回りして行動したり、会議で波風を立てずに話をまとめたりすることが「できる社員」として評価されるのです。これは裏を返せば、実際の成果が高くても、周囲と“うまくやれない”人は評価されづらいということでもあります。
また、組織内での昇進や配置転換は、実力ではなく「人間関係」で決まるケースも多く見られます。どれだけ結果を出しても、上司に気に入られなければ昇格できないという理不尽さも存在します。こうした環境では、成果主義よりも「周囲との関係性」がものを言うため、頑張っている人が損をしやすい土壌ができあがってしまいます。
つまり、「空気を読む」「波風を立てない」「上司に従順」な人が守られるのに対し、自分の意見を持ち、真面目に結果を出す人ほど浮いてしまい、評価されにくくなるのです。
真面目さが逆に評価されないケース
「真面目に働くこと」は本来、評価されるべき美徳です。しかし、現実の職場では真面目さが仇になることもあります。たとえば、規則をしっかり守り、正しい手順で仕事を進める人が、「融通が利かない」「柔軟性がない」とマイナスに捉えられることがあるのです。
また、真面目な人ほど周囲に気を遣い、自分の仕事を後回しにしてでも他人を助けてしまう傾向があります。すると、本来の業務に支障が出てしまい、結果的に評価が下がることも。一方で、要領よく立ち回る人や、手を抜いても口がうまい人が高く評価される場面もあるため、真面目な人ほど「なんで自分だけが損をしているのか」と感じやすいのです。
つまり、真面目さだけでは報われない職場では、評価の軸が歪んでおり、頑張る人が損をする構造があると言えます。
「言い返さない人」が損をする理由
多くの職場では、「反論しない人」「文句を言わない人」が、便利な存在として扱われます。つまり、何を押し付けても文句を言わずに受け入れてくれる人が、無意識のうちに都合よく使われてしまうのです。
こうした人は、他人のフォローや余計な仕事を引き受けても評価されにくく、「あの人なら大丈夫」と甘えられる傾向があります。しかも、自分では「頼りにされている」と思ってしまうため、なかなか声を上げることができません。
結果として、仕事量が増えるばかりで、評価や昇進にはつながらないという悪循環に陥ります。「自己主張をしない人」ほど損をする職場では、自分を守る術を身につけることがとても大切です。
社内政治に関わらない人が不利になることも
社内には、表に出ない人間関係の「政治」が存在することが少なくありません。誰と誰が仲が良いか、どの上司に気に入られているかなど、仕事の内容以外の部分が評価や待遇に大きく影響するケースもあります。
こうした環境では、実力や努力よりも、どれだけうまく立ち回れるかが重要になります。逆に、そうした社内政治に関わらず、ただ仕事だけをしている人は、「存在感がない」「無難すぎる」と評価されず、不利になることがあるのです。
これは特に大企業や年功序列の強い組織に多い傾向です。つまり、「まじめに仕事だけをしていれば報われる」という考え方は、必ずしも正しくないのが現実なのです。
「守られる人」の共通点と特徴
愛嬌があって憎めないタイプ
仕事ができなくても、なぜか職場で「許される人」がいます。そういう人に共通するのが、愛嬌があって周囲に安心感を与える雰囲気を持っているということです。たとえ失敗しても、どこか憎めない、笑って許してしまうような存在。こうしたキャラの人は、「あの人ならしょうがないか」と思わせる力を持っています。
愛嬌というのは単なる笑顔だけではなく、自分を取り繕わず、素直に謝れる、他人の話をよく聞くなど、日常のコミュニケーションで培われるものです。そのため、能力よりも人間関係を円滑に保つ潤滑油としての役割が重視され、結果的に守られやすいのです。
このように、「仕事ができるかどうか」よりも「一緒に働きやすいかどうか」が重要視される職場では、愛嬌のある人が得をする傾向があります。
(続きます。次は「声が大きく自己主張が強い人」からすべての項目を800文字で執筆していきます)
声が大きく自己主張が強い人
職場で“声が大きい人”がなぜか得をしている光景を見たことはありませんか?
自己主張が強く、自分の意見をしっかり伝える人は、仕事の内容に関係なく**「存在感がある」「積極性がある」**と評価されやすい傾向にあります。たとえ仕事の成果が低くても、発言が多かったり、会議で前向きな態度を見せることで「やる気がある人」として扱われるのです。
また、こうした人は自分にとって不利なことが起きそうになるとすぐに反応するため、「面倒くさいから注意しづらい」存在になります。すると上司や同僚も、波風を避けようとしてその人を守るような行動をとることがあります。これは心理学的にも「声の大きい人の意見が通りやすい」という「ドミナンス効果」が働いているためです。
つまり、声が大きく、はっきりと自己主張できる人は、能力に関係なく「扱いにくいからこそ守られる」という逆説的な評価を受けやすいのです。
上司との距離が近い人
上司との距離が近い人も、仕事の能力に関係なく守られやすい特徴があります。たとえば、ランチを一緒にしたり、飲み会に積極的に参加したり、雑談をよくする人など、人間関係を上手に築ける人は、それだけで上司に安心感を与えます。
このような関係性があると、上司はその部下に対して「親近感」や「特別感」を持つため、少しのミスや成果の低さは見逃されがちになります。いわば、“仲間内の感覚”で守られるポジションにいるのです。
また、こうした人は上司からの情報も早くキャッチできるため、社内での立ち回りもうまくなりがちです。能力がそれほど高くなくても、情報を武器にしてポジションを維持することができます。
このように、上司との人間関係の築き方ひとつで、評価や扱われ方は大きく変わるのです。
長くいるだけで評価される人
会社に長く在籍している人には、それだけで評価される傾向があります。特に中小企業や年功序列の色が強い会社では、「長くいる=信頼されている」と見なされる風潮が根強くあります。
このような人たちは、仕事のスキルが高くなくても、「あの人に聞けば何とかなる」「昔からいるから詳しい」といった経験や社内事情に精通していること自体が価値とされるのです。
また、長年勤めていることで人間関係も自然と広くなり、社内での居場所が強固になります。新しい人がそのポジションに挑戦しても、「あの人はベテランだから」と壁を感じることも多いでしょう。
結果として、能力よりも「在籍年数」で守られているように見える状況が生まれるのです。これは、会社の変化を避けたい保守的な体質とも関係しています。
トラブルメーカーなのにクビにならない理由
一見、社内で問題を起こしがちな人、いわゆる“トラブルメーカー”がなぜかクビにならずに残っていることがあります。これは不思議に思われがちですが、いくつかの理由が存在します。
まず、「辞めさせるための手続きや労力が大きい」という現実があります。日本の労働法は従業員を強く保護しているため、解雇には正当な理由が必要です。多少の問題行動では即解雇にできないのが現実です。
次に、トラブルメーカーでも「一部の業務では頼られている」「上司と仲が良い」「情報を握っている」といった理由で、意外と影響力を持っていることもあります。そうなると、波風を立てないためにあえて“触れない”ようにされ、結果的に守られてしまうのです。
また、「また問題を起こされたら困るから、刺激しないようにしている」という職場心理も働きます。これも、能力や成果ではなく「トラブル回避のための消極的な守り」というわけです。
自分が損をしないためにできる対策
「上司との関係性」の重要性を知る
自分が理不尽に損をしないためには、「上司との関係性」を戦略的に考えることが重要です。ただ仕事をこなすだけではなく、日常的なコミュニケーションの質を高めることがカギになります。
たとえば、報告・連絡・相談を意識的に行う、上司の意図をくみ取る努力をする、適度な雑談で距離を縮めるなど、人としての信頼を積み重ねることが効果的です。ここで大切なのは、「ゴマすり」ではなく、誠実さとタイミングを意識すること。
また、上司の立場やプレッシャーを理解することで、上司にとって「頼りになる存在」へと変わることができます。能力だけでなく、関係性を築く力も仕事の一部と考えることが、損をしないための大きな一歩になります。
言いたいことは言う“勇気ある自己主張”
職場で損をしないためには、「自己主張」がとても大切です。とはいえ、大声で反論したり、感情的に訴えるという意味ではありません。ここでいう自己主張とは、冷静に、自分の考えや状況をしっかりと伝えることを指します。
日本の職場では「言わない美徳」や「空気を読む文化」が根強く、自分の意見を控えてしまう人が多くいます。しかし、それでは都合のいいように使われたり、評価されないまま終わってしまうことも少なくありません。
たとえば、「この業務は今のキャパでは難しい」「この仕事の目的が分からないので確認させてください」といった形で、冷静に意見を伝えることで、誤解や過剰な期待を防ぐことができます。こうした発言は、逆に「しっかり考えている」「責任感がある」と評価されることも多いのです。
自分を守るためにも、遠慮せずに伝える力を身につけましょう。それが、真面目な人ほど損をする構造から抜け出す一歩になります。
頼られすぎないための線引き
能力がある人ほど「これもお願い」「ついでにこれも」とどんどん仕事が振られます。これは信頼されている証拠でもありますが、過剰に頼られると、自分の仕事や心の余裕を奪われる原因にもなります。
そのため、自分が壊れてしまう前に、“線引き”を意識することが大切です。「それは私の担当外です」と断るのではなく、「今抱えている仕事の納期がありますが、こちらを優先でよろしいでしょうか?」といった形で、相手に判断を委ねる形で対応するのが効果的です。
また、「一度引き受けたらずっと担当になる」という事態を防ぐためにも、“一時的な対応”であることを明確に伝えることも重要です。
頼られるのは嬉しいことですが、頼られすぎて損をしないように、自分の時間と能力を適切にコントロールしましょう。
感情ではなく「データ」で仕事を語る
自分の努力や成果をきちんと評価してもらうには、「感情」ではなく「データ」で伝えることが効果的です。「頑張ってます」「大変でした」ではなく、数値や事実をもとにアピールすることで、より説得力が増します。
たとえば、「先月の対応件数が平均より20%多かった」「クレーム件数を前月比で半減させた」といったように、見える化された成果は、誰にも否定されにくいのです。
日々の業務でこまめに数字をメモする、進捗を記録するなど、自分の仕事を「証拠」として残しておく習慣が大切です。そうすることで、いざ評価の場面や不公平を感じたときに、堂々と自分の立場を主張できる材料になります。
感情では伝わらないことも、データがあれば一目瞭然です。
職場に依存しすぎないキャリア設計
どんなに理不尽な職場でも、そこでしか生きられないと思ってしまうと、自分の価値を下げてしまいます。だからこそ大事なのは、職場に依存せず、自分のキャリアを主体的に考えることです。
まずは「今の仕事でどんなスキルが身につくか」「自分の得意をどう活かせるか」を考えましょう。そして、職場内での評価だけでなく、業界や職種全体での自分の市場価値にも目を向けることが大切です。
転職サイトに登録する、副業を始める、資格を取るなど、小さな一歩でもいいので「選べる自分」を目指すことが、精神的な余裕にもつながります。
不公平な環境に居続けることが“正義”ではありません。自分の人生は自分で守る。そのためのキャリア設計が、損をしない生き方のカギになります。
不公平な環境で自分を守る考え方
「正しさ」より「賢さ」で動く
職場の理不尽さに対して、「間違っている」「おかしい」と感じることは誰にでもあります。しかし、正しさだけで戦うと、自分が疲れてしまうのも現実です。そこで大切なのが、「正しさより賢さ」で動くという視点です。
たとえば、理不尽な要求をされたときに、正面から否定するのではなく、相手の面子を保ちつつ断るテクニックを使ったり、自分に有利な情報を静かに集めたりするなど、冷静に戦略を立てることが賢い行動です。
「なぜこの人は守られているのか?」と観察することも、職場の構造を知るヒントになります。感情に流されず、分析的に考えることが、結果的に自分を守る力となるのです。
感情をぶつけるのではなく観察する
職場で理不尽な状況に直面すると、つい怒りや不満をぶつけたくなります。しかし、感情をそのままぶつけてしまうと、周囲との関係を悪化させたり、自分の評価を下げたりするリスクもあります。だからこそ、感情的になったときほど、一歩引いて“観察する”視点を持つことが重要です。
「なぜこの人が守られているのか?」「自分の立場はどう見えているのか?」と、あえて冷静に状況を分析してみると、今まで見えてこなかった職場の構造や人間関係が浮き彫りになります。観察をすることで、感情ではなく行動で対応する戦略を立てることができます。
また、観察することで「この環境ではどう立ち回るのが最適か?」を考える余裕が生まれ、自分の価値を守るための道筋が見えてきます。感情的な反応を手放し、客観的な視点を持つことは、不公平な環境でも自分を見失わないための大きな武器になります。
「損して得とれ」の意味を見直す
「損して得とれ」という言葉がありますが、これを誤解して「耐えることが美徳」「我慢がいつか報われる」と信じすぎるのは危険です。特に、報われない環境でただ我慢を続けていると、時間もチャンスも失ってしまう可能性があります。
本当の意味での「損して得とれ」は、一時的な損を未来の利益につなげる戦略的行動を指します。たとえば、あえて面倒な仕事を引き受けて信頼を得る、難しいプロジェクトに関わってスキルを伸ばす、などです。
ポイントは、「その損が将来の得になるか?」を常に見極めること。もし未来に何の見返りも見込めないのであれば、それはただの“消耗”でしかありません。
「我慢=美徳」ではなく、戦略的に我慢すべきときと、引くべきときを判断することが、不公平な環境で自分を守る上で非常に大切です。
無理に変えようとしない選択肢もある
不公平な職場にいると、「なんとかこの状況を変えたい」と思うのが自然です。しかし、現実には自分の力だけではどうにもならないこともあります。そんなときは、無理に変えようとせずに、「距離を置く」「諦める」「自分のペースを保つ」といった選択肢もアリなのです。
たとえば、職場の空気に無理に合わせず、自分のペースを貫くことで、ストレスを減らしつつ働き続けることができるかもしれません。また、同僚や上司の理不尽な言動に対しても、「そういう人なんだ」と割り切ることで、無駄に疲れずに済みます。
無理に正義を押し通そうとすると、自分が傷つきやすくなります。だからこそ、「期待しすぎない」「変えようとしすぎない」という姿勢も、長く働き続けるための知恵のひとつです。
最終的には「転職」も視野に
どれだけ対策をしても、どうしても変わらない、報われないと感じた場合は、「転職」も立派な選択肢のひとつです。現状に不満があるのに何も動かないでいると、精神的にも体力的にも削られていきます。それはとてももったいないことです。
最近では、転職市場も広がり、未経験からでも挑戦できる業界や、働きやすさを重視した企業も増えています。「今の職場がすべてではない」という視点を持つことで、心にも余裕が生まれます。
まずは情報収集からでもOKです。転職サイトやエージェントを活用することで、自分の市場価値を客観的に知ることができます。それだけでも、「自分には選択肢がある」と思えるようになり、理不尽な職場に振り回されない自分を作ることができるのです。
まとめ
「仕事ができない人が守られる」と感じる場面には、さまざまな理由と構造があります。評価の基準が成果だけでなく、人間関係や印象、上司の都合によって左右されることも多いため、「頑張っているのに報われない」と感じる人が損をしてしまう現実もあるのです。
しかし、その中で自分を守り、損をしないための行動や考え方も存在します。上司との関係性を見直す、自己主張する勇気を持つ、データで成果を伝える、そして職場に依存しすぎないキャリア設計などがその例です。
大切なのは、「理不尽さに飲み込まれないこと」。感情に流されず、冷静に観察し、自分なりの戦略で立ち回ることで、不公平な環境の中でも自分の価値を守ることができます。そして、必要ならば転職という選択も恐れず、「選べる自分」でいることが、最も強い武器になるのです。