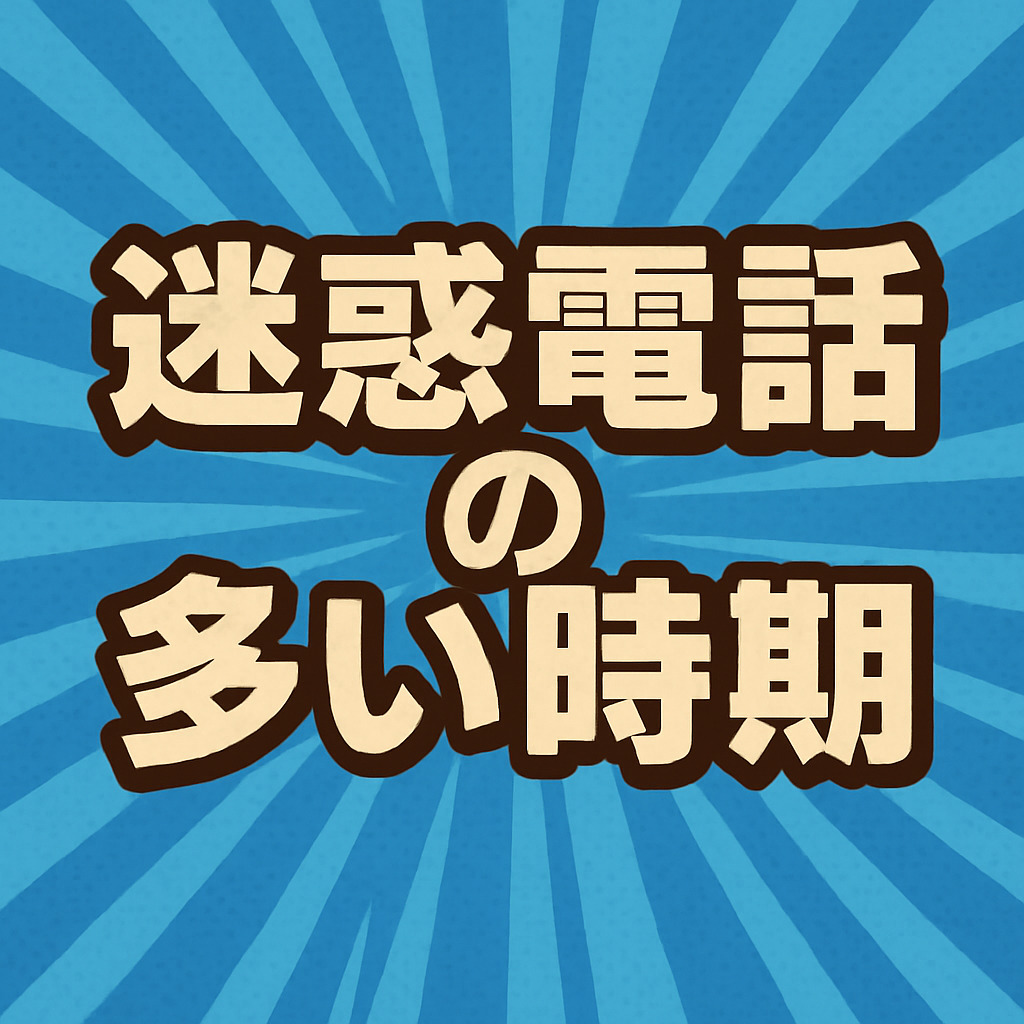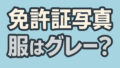最近、知らない番号からの電話がやたらと多くないですか?
しかも出てみると、「支払いが遅れている」「当選しました」「ご家族が事故に…」など、不安をあおる内容ばかり。もしかすると、それはただの営業電話ではなく、本物の詐欺電話かもしれません。
特に特定の時期になると、なぜか増えるこの“迷惑電話”。実は、詐欺グループには「狙いやすい時期」があり、行動パターンがしっかり存在するのです。
この記事では、迷惑電話が多くなる時期の傾向と理由、そして今すぐできる対策や通報方法までをわかりやすく解説します。スマホユーザーも、ご年配のご家族を守りたい方も、必見の内容です!
なぜ「特定の時期」に迷惑電話が増えるのか?
電話詐欺グループの行動パターン
迷惑電話の多くは、組織的に動いている詐欺グループによって行われています。これらのグループには「狙いやすいタイミング」があります。例えば、月末や給料日の後は、一般家庭にお金があると見込んで動きが活発になります。また、詐欺グループの中には「営業日」「カレンダー」に合わせて動いているケースもあり、週明けや連休明けなど、人々が気が緩みがちな時期を狙う傾向があります。
さらに、警察や自治体の摘発を避けるために、「短期間で集中してかける」動きもあります。一時的に大量の迷惑電話がかかってきて、その後はピタッと止まるというケースは、こういった理由が背景にあります。つまり、迷惑電話には「季節性」と「タイミング性」があるのです。
電話をかける側も、効率よく成果を上げたいと考えているため、確率が高そうな「時期」を選んで仕掛けてきます。特に、金銭トラブルや不安をあおりやすい季節が狙われやすいという特徴があります。
年末年始とボーナス時期の関係
年末年始は、迷惑電話や詐欺電話が最も多くなる時期のひとつです。その理由の一つが「ボーナス」です。多くの企業では12月に冬のボーナスが支給されるため、詐欺グループにとっては“狙い目”になります。現金を手にする人が増えるこの時期、電話による詐欺が急増する傾向があります。
また、年末年始は人の出入りや帰省などで、家族構成が一時的に変わる家庭もあります。そのため「息子が事故を起こした」「孫がトラブルに巻き込まれた」といった“オレオレ詐欺”の手口が成功しやすいタイミングでもあります。
さらに、金融機関が休みに入る直前を狙って「今すぐ振り込んで」と急かす手口も多く、焦って対応してしまう人もいます。年末は忙しい時期でもあり、冷静さを欠きやすく、詐欺グループにとっては格好のチャンスとなっています。
新学期・新生活シーズンの狙い目
4月の新学期や新生活が始まる季節も、迷惑電話が増えるタイミングとして知られています。この時期は、進学・就職・転居などで生活環境が大きく変化する人が多く、個人情報が外部に漏れやすい状況でもあります。
例えば、引っ越し先でのネット契約やクレジットカード登録などを行った際、どこかから情報が流出し、詐欺グループがその情報を元に連絡してくるケースがあります。「引っ越し業者を名乗る」「新しい携帯会社のキャンペーンを装う」など、新生活に関連した迷惑電話がよく見られるのがこの時期の特徴です。
また、新社会人や一人暮らしを始めたばかりの若者は、詐欺に慣れていないこともあり、警戒心が薄いことが多いです。そのため、詐欺師にとっては“狙いやすい”ターゲットとなります。
国や自治体の給付金発表後に増加
過去の例でも明らかですが、政府や自治体が「給付金」や「支援金」を発表した後、その情報に便乗した詐欺電話が急増する傾向があります。たとえば、コロナ禍の際には「給付金の手続き代行」や「還付金の振込口座確認」を装った詐欺が多発しました。
これは、ニュースなどで広く報道された情報を悪用する典型的な例で、人々が「お金がもらえる」と期待している心理を逆手に取ってきます。しかも、実在する制度や組織を名乗ることで、信用させるような仕掛けがなされており、非常に巧妙です。
このような詐欺は、特に高齢者に被害が多く、家族との情報共有や、最新情報へのアンテナが重要になります。「給付金の案内は原則郵送」などの正しい知識を事前に伝えておくことが、迷惑電話対策につながります。
季節のイベントと連動する迷惑電話
迷惑電話は、季節のイベントと連動するケースもあります。例えば、バレンタイン・母の日・父の日・クリスマスといったギフトシーズンでは、「商品を送ったけど配達トラブルがあった」として不安をあおるような電話がかかってくることがあります。
また、イベント前に「キャンペーンに当選した」と称して個人情報を聞き出す手口も存在します。こういった迷惑電話は、詐欺だけでなく過剰なセールスや個人情報収集を目的としているケースもあります。
特にネットショッピングの利用が増えるイベント時期は、配達や注文確認を装った電話が増えるため、注意が必要です。公式のカスタマーサポートを装う迷惑電話にも十分な警戒が必要です。
最も迷惑電話が増えるのはいつ?データで解説
月別・季節別の迷惑電話発生傾向
迷惑電話の件数は、実は月によって大きく変動します。警察庁や総務省が公開しているデータによると、特に多いのは12月、4月、8月です。それぞれの月に共通するのは、「人の動きが多い」「お金が動く」「気が緩みやすい」という特徴です。
例えば、12月は年末で気忙しく、ボーナスも支給されるため金銭トラブルを狙った電話が急増します。4月は新生活が始まる季節で、引っ越しや進学、就職による個人情報の動きが活発になります。そして8月はお盆休みなどで実家に戻る人も多く、高齢者と離れて暮らす家族を狙ったオレオレ詐欺などが増える傾向にあります。
また、天候や自然災害の後なども迷惑電話が急増する傾向があります。特に「義援金詐欺」や「災害保険の確認」と称した電話が増えるので、注意が必要です。
総務省や警察庁の統計から読み解く
迷惑電話の増加傾向を正しく理解するには、信頼できるデータを見るのが一番です。総務省や警察庁は、特殊詐欺に関する統計を毎年発表しており、その中には迷惑電話に関する情報も含まれています。たとえば、警察庁の「特殊詐欺発生状況」では、月別の相談件数や被害額などが公開されており、どの月に被害が集中しているかがわかります。
直近のデータでは、12月と4月、そして夏季休暇シーズンである8月に、相談件数が急増している傾向が見られます。これは前述の通り、「金銭が動く」「人の気が緩む」「情報が動く」時期と一致しています。こうした情報は、警察庁の公式サイトや都道府県の警察本部のホームページなどで誰でも確認することができます。
また、総務省の「迷惑電話対策の取り組み」では、電話会社やアプリによる対策の実施状況や、消費者からの苦情件数の推移などもまとめられており、被害の全体像がわかりやすくなっています。迷惑電話対策を考えるうえで、こうした公的な統計をチェックする習慣はとても有効です。
SNSで話題になる「迷惑電話シーズン」
近年、SNSで「またこの時期が来たか…」「○○の詐欺電話が増えてる」といった投稿が見られるようになりました。実はこれらのSNS上の話題も、迷惑電話の“シーズン”を予測するのに役立ちます。X(旧Twitter)やInstagramなどで「迷惑電話」「詐欺電話」と検索してみると、ユーザーのリアルな声が多数見つかります。
特に注目したいのが「同じ電話番号からの着信報告が一斉に増える」ようなケースです。これは詐欺グループが複数のターゲットに一斉に電話をかけている証拠です。ある種の“迷惑電話キャンペーン”が行われていると考えられます。
さらに、SNSでは「こういう手口だった」「この番号には出るな」など、有益な情報が共有されることも多いため、早期に気づける可能性もあります。迷惑電話が流行している時期にはSNSで情報を集めて、自分の身を守るための参考にするのも効果的です。
高齢者を狙う時期別の特徴
高齢者を狙った迷惑電話は、特定の時期に集中する傾向があります。特に多いのが「年金支給日」の前後です。日本では偶数月の15日に年金が支給されるため、2月、4月、6月、8月、10月、12月の中旬は、詐欺グループが高齢者に連絡を取りやすい時期とされています。
この時期には、「年金の手続きに不備がある」「医療費の還付がある」など、もっともらしい理由をつけて個人情報や銀行口座を聞き出そうとするケースが多く報告されています。また、高齢者はスマートフォンやIT機器に不慣れな場合も多く、電話を信じてしまう傾向があるため、家族による声かけが重要です。
さらに、年末年始やお盆などの帰省シーズンに家族と離れて過ごしている時期も、狙われやすくなります。「息子さんが事故を起こした」などのオレオレ詐欺がこのタイミングで増えるのはそのためです。高齢の家族がいる家庭では、時期ごとのリスクを意識した見守りが大切です。
実際の相談件数が多い月とは?
迷惑電話や詐欺に関する相談件数は、消費生活センターや警察のデータから確認することができます。国民生活センターの「PIO-NET(パイオネット)」によると、特に相談が集中するのは12月と1月です。これは年末年始に向けて「今すぐ対応が必要」と迫るような内容の電話が増えるからです。
また、4月の新年度開始時期にも「登録情報の更新が必要」「保険の切り替えに関する案内」などといった迷惑電話が多くなる傾向があります。これらは一見、必要な手続きのように見えますが、実は巧妙に作られた詐欺の一環です。
表にしてみると、迷惑電話の多い月は以下の通りです。
| 月 | 特徴的な迷惑電話内容 | 相談件数傾向 |
|---|---|---|
| 1月 | 正月明けの振込詐欺 | 多い |
| 4月 | 新生活関連の勧誘 | 多い |
| 6月 | 年金関連・医療詐欺 | 中程度 |
| 8月 | 帰省シーズン狙い | 多い |
| 12月 | ボーナス・年末詐欺 | 非常に多い |
こうした月別の傾向を把握しておくと、家族全体で注意を高めることができ、被害を未然に防ぐ効果があります。
迷惑電話の手口はどう変化している?最新の傾向
AI音声・自動音声を使った詐欺電話
近年急増しているのが、AI音声や自動音声を利用した迷惑電話です。以前は人間のオペレーターが直接電話をかけてくることが一般的でしたが、今ではボイスボットによる自動音声案内が巧妙に使われています。「こちらは○○銀行です」「保険会社の○○です」といった本物そっくりの声で案内が始まり、「本人確認のため番号を入力してください」と指示されるケースもあります。
AIの技術が進化しており、実在する企業の声のトーンや話し方を真似てくるケースもあるため、非常に信じやすくなっているのが特徴です。さらに、音声案内の途中で人間のオペレーターにつながるような仕組みもあり、まるで本物の電話窓口のような作り込みがされていることもあります。
このようなAI音声詐欺は、時間帯や人手を気にせず大量に発信できるため、コスト面でも詐欺グループにとってメリットがあります。対策としては、知らない番号からの着信はすぐに出ない、音声案内で「個人情報の入力」を求められたら即切る、という基本行動が大切です。
なりすまし(家族・警察・役所)の増加
なりすましによる迷惑電話は昔からありますが、最近はさらに巧妙になってきています。家族や親族を装って「事故を起こした」「スマホを壊して電話番号が変わった」といった“オレオレ詐欺”が進化し、警察官や市役所職員を名乗るケースも増えています。
特に警察や役所を名乗る詐欺電話は、「あなたの口座が不正に使われています」「キャッシュカードを預かります」などと、不安をあおって金銭や個人情報を引き出そうとする手口が一般的です。これらの手口は、一見信頼できそうな団体名を使うため、冷静さを失ってしまいやすい点が危険です。
さらに、最近では本当に存在する部署名や職員名を使ってくるケースもあり、インターネットで検索しても「実在する」ため、騙されてしまう人が後を絶ちません。対応策としては、必ず相手の名前・所属部署・電話番号を控え、公式の番号に折り返すことが基本です。
ワン切りや折り返し詐欺の手口
「ワン切り詐欺」や「折り返し詐欺」は、一度だけ着信を残して興味を引き、かけ直してきた相手に通話料を課すタイプの詐欺です。これらの電話は、見慣れない番号、特に国際電話番号(+1、+44、+60など)や、携帯電話と似たような番号からかかってくるのが特徴です。
かけ直すと、延々と保留音や無言状態が続き、高額な通話料金を請求される仕組みになっています。また、かけ直した際に自動音声で誘導され、プレミアム料金が発生するサービスに勝手に接続されてしまうケースもあります。
こうした手口に共通するポイントは「かけ直させること」にあります。対策としては、知らない番号に折り返し電話をしない、番号をGoogleで検索して「迷惑電話報告」があるか確認することが大切です。スマホの設定で国際電話をブロックするのも効果的です。
「○○キャンペーン中です」型の営業電話
一見すると詐欺ではなく「営業電話」に見えるパターンですが、実際は迷惑目的や情報搾取が目的の電話もあります。「今なら光回線が半額」「無料でお風呂のリフォーム見積もりします」など、聞こえの良い話でアポイントを取り、最終的に高額な契約を迫るという流れが一般的です。
こういった電話は、電話番号を無作為に発信する自動ダイヤルを使って大量にかけられており、特に「日中に自宅にいる人(高齢者など)」が狙われやすい傾向にあります。中には、話を聞くだけで情報が売られ、他の業者からも電話がくるようになることも。
営業電話に対しては、「電話帳に登録されていない番号は着信拒否」「断っても何度もかかってくる場合は消費生活センターに相談」という対応を徹底しましょう。
無料アプリやSMS経由での迷惑通知
最近では、電話だけでなくSMS(ショートメッセージ)やアプリを通じた迷惑通知も増加しています。「宅配業者からのお知らせ」「未払い料金があります」といった文面で、偽サイトへ誘導し、個人情報やクレジットカード情報を盗もうとする手口です。
特に、URL付きのSMSは要注意です。これらのリンクをクリックすると、偽サイトに飛ばされるだけでなく、スマホにウイルスをインストールさせられる危険もあります。無料の天気アプリや占いアプリなど、一見無害そうなアプリが個人情報を収集していることもあります。
対策としては、不審なSMSは絶対にリンクを開かないこと。さらに、スマートフォンの「迷惑メッセージフィルター」機能や、セキュリティアプリを導入することでリスクを大きく減らせます。
今すぐできる迷惑電話対策の基本と応用テク
電話帳に登録されていない番号をブロック
スマートフォンには、電話帳に登録されていない番号からの着信を自動でブロックする機能があります。iPhoneや一部のAndroid機種では、「不明な発信者を消音」や「知らない番号をブロック」といった設定が可能です。これをオンにすることで、知らない番号からの着信が鳴らなくなり、迷惑電話のストレスを大きく減らすことができます。
ただし、この機能を使うと、病院や配送業者など必要な電話もブロックされることがあるため注意が必要です。対策としては、よく使う施設やお店の番号をあらかじめ電話帳に登録しておくことが重要です。また、電話が鳴らない代わりに留守番電話機能をオンにしておくことで、重要なメッセージを後から確認できます。
この方法は、特に高齢者のスマートフォンにも設定しておくと効果的です。設定自体は数分でできる簡単なもので、日々の安心感が大きく変わります。
キャリア別の迷惑電話対策設定(docomo/au/SoftBank)
各携帯キャリアでは、迷惑電話対策用のサービスを無料または低価格で提供しています。たとえば、docomoの「迷惑電話ストップサービス」や、auの「迷惑電話撃退サービス」、SoftBankの「ナンバーブロック」などがあり、どれも着信の時点で迷惑電話を検知して警告してくれます。
これらのサービスでは、詐欺に使われる可能性の高い番号をあらかじめデータベース化しており、着信時に「この電話は迷惑の可能性があります」と画面に表示されるようになっています。これだけでも、知らない番号からの電話に対して警戒心を持つきっかけになります。
一部サービスは有料(月額100〜300円程度)ですが、被害のリスクを考えると非常にコスパの良い対策といえるでしょう。キャリアごとに公式アプリや設定方法が異なるため、自分の契約しているキャリアのホームページで最新情報を確認することをおすすめします。
iPhone・Androidでできる機能設定
iPhoneとAndroidには、それぞれ迷惑電話に対応するための設定機能が備わっています。iPhoneでは「設定」→「電話」→「不明な発信者を消音」をオンにすることで、連絡先にない番号の着信音が鳴らなくなり、履歴には残る仕組みになっています。
Androidの場合は機種によって異なりますが、「Googleの電話アプリ」を使っている場合は、「迷惑電話の識別とブロック」機能を有効にすることで、不審な番号からの着信時に警告が表示されます。さらに、着信を自動で拒否する設定も可能です。
これらの設定は、スマホの操作に慣れていない人でも比較的簡単に行えるようになっています。迷惑電話が頻繁にかかってくるようになったら、まずはスマホの基本設定を見直すところから始めましょう。
迷惑電話チェッカーアプリの活用法
迷惑電話をブロックするための専用アプリも非常に有効です。代表的なものに「Whoscall(フーズコール)」「迷惑電話ストッパー」「電話帳ナビ」などがあります。これらのアプリは、世界中のユーザーが報告した迷惑電話番号のデータベースを元に、着信時に「迷惑電話の可能性があります」と警告を出してくれます。
特に「Whoscall」は、Google PlayとApp Storeの両方で高評価を得ており、着信時の情報表示に加えて、番号検索機能や通話履歴の分析も可能です。無料プランでも十分に使える機能が揃っているため、スマホに1つ入れておくだけで安心感が違います。
ただし、アプリを使う際は個人情報の取り扱いに注意が必要です。インストール時には「通話履歴へのアクセス」や「連絡先へのアクセス」などの権限を求められることがあるため、信頼できる開発元のアプリを選ぶことが大前提です。
家族や高齢者と共有すべき対策情報
迷惑電話対策は個人だけでなく、家族全体での情報共有がとても重要です。特に高齢者は、電話が生活の中心となっていることが多く、詐欺や営業電話のターゲットになりやすい存在です。家族が積極的に情報を伝えることが、被害を未然に防ぐカギとなります。
例えば、「知らない番号から電話が来ても絶対に折り返さない」「役所や銀行は電話で口座情報を聞いてこない」といった基本的な知識を、繰り返し伝えることが効果的です。また、スマートフォンや固定電話に迷惑電話ブロック機能があることを一緒に確認し、必要に応じて設定してあげることも重要です。
さらに、「迷惑電話が増える時期」についても家族で共有しておくと、「この時期は注意しよう」と意識を高めることができます。家族が一丸となって対応することで、詐欺グループのターゲットになりにくくなるのです。
それでも来るなら?迷惑電話の通報&相談窓口
警察庁の「特殊詐欺110番」への通報方法
迷惑電話が詐欺や犯罪の可能性を含んでいる場合は、ためらわず警察に通報することが最も大切です。全国の警察には「特殊詐欺110番」や「サギ110番」といった専用の窓口が設置されており、直接電話やメールで相談することができます。
通報の際は、できるだけ以下の情報を伝えるとスムーズです:
-
電話がかかってきた日時
-
電話番号(発信者の番号)
-
電話で言われた内容
-
相手の名乗った名前や団体名
-
要求された内容(お金、個人情報など)
警察は通報をもとに詐欺グループの行動パターンを分析し、被害の拡大を防ぐための対策を講じています。特に、同じ番号から複数の被害が出ている場合は、早期の検挙につながる可能性も高くなります。
また、実際に被害にあっていなくても「怪しい」と思った段階で相談することが推奨されています。被害を未然に防ぐ行動が、自分や家族、地域の安全を守る第一歩です。
各都道府県の消費生活センター情報
迷惑電話や詐欺まがいの営業電話については、消費生活センターも心強い相談窓口です。各都道府県に設置されており、住んでいる地域に関係なく誰でも無料で相談できます。全国共通の電話番号「188(いやや!)」にかけると、最寄りのセンターにつながります。
消費生活センターでは、以下のような支援を行っています:
-
迷惑電話に関する法的なアドバイス
-
契約トラブルへの対処法
-
被害の防止策についての説明
-
必要に応じて行政機関との連携
また、迷惑電話の情報は統計として蓄積され、国や自治体の対策に活かされます。通報することで、社会全体の対策強化につながるのも大きなメリットです。
高齢者やスマホ操作が苦手な人でも、電話一本で相談できるため、家族が一緒にかけてあげるのも良いでしょう。
携帯キャリアへの通報方法まとめ
携帯電話会社も、迷惑電話の情報を受け付けており、サービス向上やブロックリストの強化に活用しています。主要キャリア3社の通報方法は以下の通りです。
| キャリア | 通報方法 | 備考 |
|---|---|---|
| docomo | 「ネットトラブルあんしんサポート」からWEB通報 | My docomoからも可能 |
| au | 「迷惑メール・電話通報窓口」フォームあり | サイトでの通報推奨 |
| SoftBank | My SoftBank内に迷惑電話報告機能あり | 専用アプリ「迷惑電話ブロック」経由も可 |
また、通報だけでなく、自動で迷惑電話番号をブロックする設定やアプリの案内も行ってくれるため、困った時はカスタマーサポートに相談するのもおすすめです。
格安SIMユーザーの場合でも、キャリアによっては対応窓口があるので、契約しているMVNOのサポートページを確認しましょう。
LINEやTwitterでのリアルタイム報告
最近では、SNSを使った迷惑電話のリアルタイム共有も広がっています。特にLINEの「迷惑電話情報共有グループ」や、X(旧Twitter)での「#迷惑電話」「#詐欺電話」などのハッシュタグ検索が効果的です。
実際にかかってきた番号を投稿することで、他の人の被害を防ぐことができ、逆に自分も最新の手口を知ることができます。また、スマホの迷惑電話アプリによっては「報告ボタン」を押すだけで、クラウド上に情報が共有され、他のユーザーに警告が表示される仕組みもあります。
これらのリアルタイム共有によって、詐欺グループの活動が広く知られ、結果的に被害が減る効果が期待できます。スマホを使っているなら、SNSやアプリの共有機能をうまく活用することも大切です。
通報で得られるメリットと効果
迷惑電話を通報すると、単なる「個人の対策」にとどまらず、社会全体への貢献にもつながります。例えば、自分が受けた迷惑電話の番号が通報され、アプリやキャリアでブロック対象として登録されれば、他の人が被害を受ける可能性が大きく減ります。
また、通報の積み重ねによって警察や自治体が動き、詐欺グループが摘発されることもあります。実際、過去の報道でも「市民の通報がきっかけで犯人が逮捕された」という事例が多く存在します。
さらに、通報することで自身の危機意識も高まり、「次からは気をつけよう」という心構えが生まれるのもメリットのひとつです。迷惑電話は「放置しない」「声を上げる」ことが被害の連鎖を断ち切る第一歩なのです。
まとめ
迷惑電話は、単に「うるさい」「面倒」といったレベルを超えて、詐欺や個人情報流出といった重大なリスクにつながる危険な存在です。特に、年末年始や新年度、ボーナス支給時期といった「お金」や「情報」が動くタイミングに集中して発生する傾向があります。
AI音声を活用した新しい手口や、家族・警察・公的機関を装う巧妙ななりすましも増えており、手口は年々進化しています。しかし、スマホの設定変更、迷惑電話ブロックアプリの導入、そして家族との情報共有など、簡単にできる予防策もたくさんあります。
そして、迷惑電話が来てしまった場合には、通報することで自分だけでなく他人を守ることができます。国や自治体、携帯キャリア、SNSを活用し、「迷惑電話に強い社会」を作ることが大切です。
迷惑電話を「受け流す時代」は終わりました。
これからは「賢く対処する時代」です。
自分自身と、大切な人を守るために、今できることから始めていきましょう。