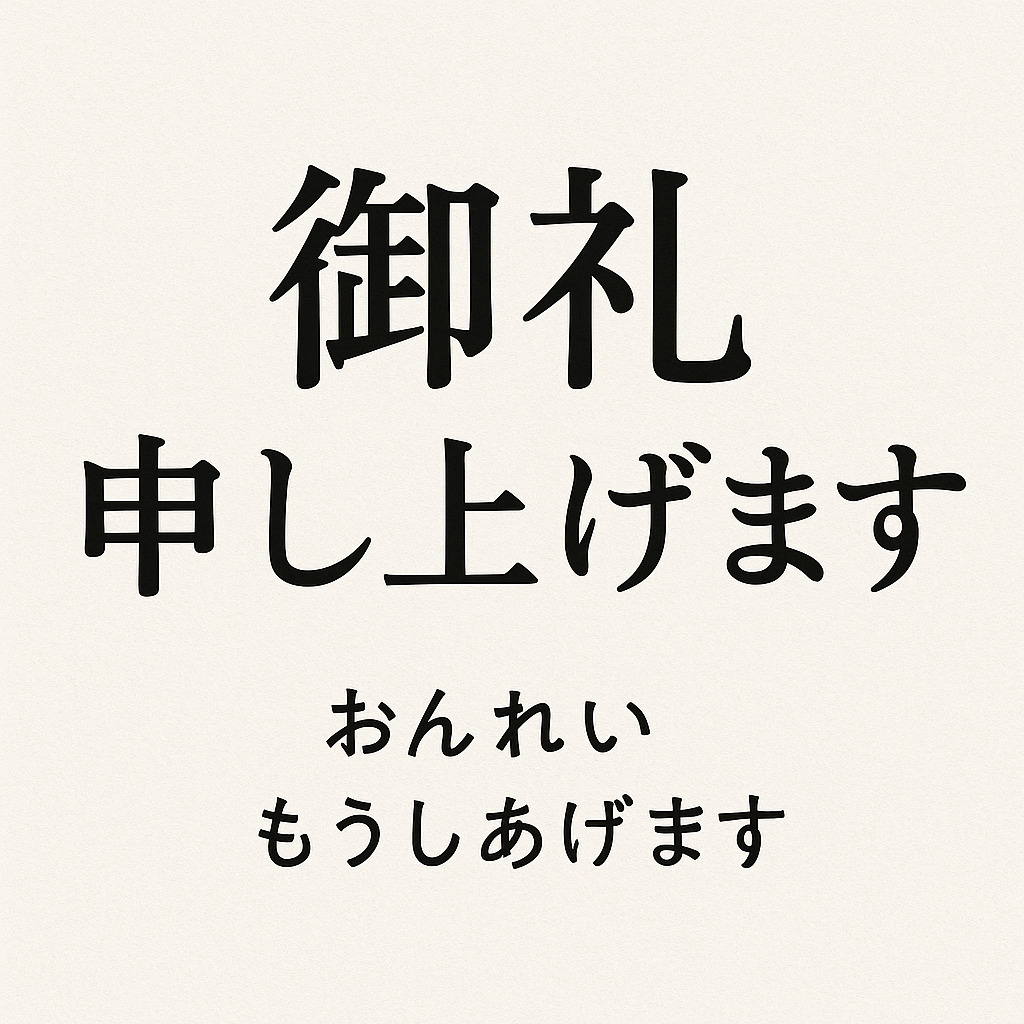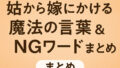ビジネスメールやフォーマルな挨拶状でよく使われる「御礼申し上げます」。
でも、実は読み方を間違えていたり、正しい使い方を知らずに使ってしまっている人も多いのではないでしょうか?
この記事では、「御礼申し上げます」の正しい意味や読み方、使い方の例文から、よくある間違い、そして似た表現との違いまでを徹底的にわかりやすく解説します。
言葉の選び方ひとつで、あなたの印象は大きく変わります。ぜひこの記事で、正しい敬語マナーを身につけましょう。
=「御礼申し上げます」の正しい意味と使い方|ビジネスでも間違えない敬語マナー=
正しい意味と読み方を解説
「御礼申し上げます」は何と言う意味?
「御礼申し上げます」という言葉は、相手に対して深い感謝の気持ちを表す、とても丁寧な日本語表現です。
特にビジネスの場面や改まった場面で使われることが多く、「ありがとうございました」よりも丁寧な印象を与えます。
「御礼」は「お礼」の丁寧な言い方で、「申し上げます」は「言う」の謙譲語です。
つまり、「感謝の気持ちを申し上げます」という意味になり、自分をへりくだって相手に敬意を払っている表現です。
日常的な会話ではあまり使われませんが、以下のような状況では非常によく使われます:
-
取引先へのお礼メール
-
面接後のメールや手紙
-
結婚・出産などの報告状
-
弔事やお見舞いのお礼状
このように、「御礼申し上げます」は相手に対する敬意を込めて使う、非常にフォーマルな感謝表現なのです。
読み方のポイントと間違いやすい読み方
「御礼申し上げます」の正しい読み方は:
おんれい もうしあげます
と読みます。
ここで注意したいのが、「御礼(おんれい)」の読み方です。「ごれい」と読む方も稀にいますが、これは間違いです。
また、「申し上げます」は「もうしあげます」と丁寧に発音するのがポイントで、口語で早口になると「もっしゃげます」などと崩れて聞こえることもあるため、フォーマルな場でははっきり発音するようにしましょう。
間違った読み方をしてしまうと、せっかくの丁寧な言葉も印象が悪くなってしまうことがあります。
特に電話や音声メッセージなど、声で伝える場面ではしっかり発音することを心がけましょう。
「御礼」だけでは失礼なのか?
ビジネスメールなどで「御礼申し上げます」の代わりに「御礼申し上げます」と書かずに、単に「御礼」とだけ書いてしまう方もいますが、これは注意が必要です。
「御礼」は名詞で、「感謝の気持ちそのもの」を指す言葉です。たとえば、
-
「御礼として商品券をお渡しします」
-
「御礼の品をお送りいたします」
といったように、何か行動や物とセットで使うのが自然です。
一方で、「御礼申し上げます」は動詞的な表現になり、「感謝の気持ちを述べる」という意味が明確に伝わります。
そのため、ビジネスシーンで感謝の気持ちを文面で伝える場合には、単に「御礼」とするのではなく、「御礼申し上げます」ときちんと書いた方が、丁寧で誠意のある印象になります。
謙譲語としての「申し上げます」の役割
「申し上げます」という言葉は、敬語の中でも「謙譲語」に分類されます。
謙譲語とは、自分をへりくだることで相手を立てる敬語の形式です。たとえば、
-
「言う」 → 「申し上げる」
-
「見る」 → 「拝見する」
-
「行く」 → 「伺う」
のように変化します。
「御礼申し上げます」の「申し上げます」は、「私は感謝の言葉を申し上げます」という意味で使われ、自分の行動(感謝の意を述べる)をへりくだって表現しているのです。
これにより、相手に対する敬意や丁寧さがグッと高まります。
謙譲語をうまく使えると、社会人としての信頼度も上がりますので、「申し上げます」のような表現をしっかり覚えておきましょう。
他の言い回しとの違い(感謝申し上げます、ありがとう など)
「御礼申し上げます」に似た表現として、以下のような言葉があります:
| 表現 | 意味・使う場面 | フォーマル度 |
|---|---|---|
| 感謝申し上げます | 「感謝」の気持ちを強調したい時 | 高い |
| ありがとうございます | 日常的な感謝の表現 | 中程度 |
| お礼申し上げます | 「御礼」より少しくだけた印象 | 中程度 |
| 深く御礼申し上げます | より深い感謝の意を伝えたい時 | 非常に高い |
「御礼申し上げます」は、感謝の気持ちを丁寧に伝える中でもスタンダードであり、幅広いビジネスシーンに対応できる表現です。
相手や場面に応じて、これらの言い回しを使い分けられると、より洗練された印象を与えることができるでしょう。
ビジネスシーンでの使い方例
メールで使う時の正しい文例
ビジネスメールでは「御礼申し上げます」はとてもよく使われます。
たとえば、以下のような文面がよく見られます。
件名:〇〇に関する御礼
株式会社○○
〇〇様
いつも大変お世話になっております。株式会社△△の□□でございます。
このたびは〇〇の件につきまして、迅速かつ丁寧なご対応を賜り、誠にありがとうございます。
心より御礼申し上げます。
今後とも変わらぬお付き合いのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
このように、「御礼申し上げます」は文末に使うことで丁寧に感謝の気持ちを伝えることができます。
メールではテンプレートとして覚えておくと、いざという時に非常に役立ちます。
ビジネスシーンでの使い方例
面接・電話対応での活用法
就職活動の面接や、ビジネスにおける電話対応では、言葉遣い一つで印象が大きく変わります。そんな中、「御礼申し上げます」は非常に好印象を与えるフレーズとして活用できます。
たとえば、面接後に以下のように使うと丁寧な印象になります。
「本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。」
このような一文をメールやお礼状に入れるだけで、あなたの礼儀正しさが伝わります。
電話応対の場合も同様です。お客様対応や取引先とのやり取りの最後に、
「このたびは、○○の件につきましてご丁寧な対応を賜り、誠にありがとうございました。改めて御礼申し上げます。」
と伝えると、信頼感を持ってもらいやすくなります。
ただし、口頭で使う場合は、あまり硬くなりすぎると不自然に聞こえることもあるので、声のトーンやタイミングに注意しましょう。
使いこなせば、ビジネスマナーの一歩先をいく印象を与えることができます。
上司や取引先へのマナーとしての注意点
上司や取引先に「御礼申し上げます」を使う際は、使い方を間違えると逆効果になる場合もあります。
とくに注意したいのは、他の言葉とのバランスやタイミングです。
たとえば、メールの冒頭でいきなり「御礼申し上げます」と書くのはやや唐突です。まずは「いつもお世話になっております」などの定型の挨拶文を入れてから感謝を述べるのが自然です。
また、次のような点にも注意しましょう。
-
感謝の理由を明確に書く(「何に対しての御礼か」を必ず添える)
-
連絡が遅れた場合は先にお詫びを入れる(例:「ご連絡が遅くなり申し訳ありません。改めて御礼申し上げます。」)
-
同じ文中で何度も使いすぎない(くどく感じられる)
丁寧であることは重要ですが、形式的すぎると逆に冷たく感じられることもあります。相手との関係性や状況に応じて、適度に使い分けましょう。
「御礼申し上げます」のNG例と改善例
以下に、よくある誤った使い方と、それをどう改善すべきかを具体例でご紹介します。
| NG例 | 改善例 | 解説 |
|---|---|---|
| ○○様には御礼申し上げます。 | このたびは○○についてご対応いただき、心より御礼申し上げます。 | 理由が不明で唐突な印象になるため、具体性を持たせる。 |
| ありがとうございました。御礼申し上げます。 | このたびは誠にありがとうございました。改めて御礼申し上げます。 | 同じ意味を重ねる場合、「改めて」などの言葉を添えると自然。 |
| 御礼を言いたいです。 | 心より御礼申し上げます。 | カジュアルな表現はビジネスでは不適切。敬語に統一する。 |
このように、「御礼申し上げます」は正しく使えば非常に良い印象を与えますが、誤った使い方をしてしまうと敬語が逆効果になる可能性もあるため注意が必要です。
場面別・簡単敬語フレーズ集
以下に、「御礼申し上げます」を含むビジネスでよく使える定番フレーズを場面別にまとめました。
| シーン | フレーズ例 |
|---|---|
| 初対面の挨拶 | 「お忙しい中、お時間をいただき誠にありがとうございます。御礼申し上げます。」 |
| お礼メール | 「このたびは迅速なご対応を賜り、心より御礼申し上げます。」 |
| 取引成立後 | 「○○の件、無事に完了いたしました。深く御礼申し上げます。」 |
| サポート対応後 | 「丁寧なご説明とご対応をいただき、誠にありがとうございました。御礼申し上げます。」 |
| アポイント後 | 「本日は貴重なお時間をいただき、御礼申し上げます。」 |
このようなフレーズをいくつか覚えておくと、あらゆるビジネスシーンで即座に対応できるようになります。
相手に誠意が伝わるような言い回しを心がけましょう。
よくある誤用と注意点
「御礼申し上げます」を使ってはいけないケース
「御礼申し上げます」は丁寧な言葉ですが、すべての場面で使えるわけではありません。
特に次のような場面では注意が必要です。
-
上司とのカジュアルな会話
-
あまりにも堅すぎる印象を与えることがあります。
-
-
日常の軽いやり取り
-
例えば同僚にちょっとした資料をもらった時に「御礼申し上げます」と言うと、かえって大げさに感じられます。
-
-
冗談っぽい文脈
-
軽いノリの中で使うと不自然になることがあります。
-
また、悲しみの場(訃報など)で使う際も、「御礼申し上げます」ではなく「お悔やみ申し上げます」「ご厚情に深く感謝申し上げます」など、状況に適した言葉に置き換える必要があります。
TPOに応じて正しく使い分けることが、社会人としてのマナーでもあります。
二重敬語になっていないか?
敬語表現を重ねすぎると「二重敬語」になり、不自然になることがあります。
たとえば、
「御礼を申し上げさせていただきます」
という表現は、
-
「申し上げる(謙譲語)」
-
「させていただく(謙譲語)」
と、二重になってしまっているため、やや不自然です。
正しくはシンプルに、
「御礼申し上げます」
だけで十分丁寧です。
敬語は足し算ではなく、「ちょうどいい丁寧さ」で止めるのが美しい表現になります。
「御礼申し上げます」と似た表現の使い分け
「感謝申し上げます」との違い
「御礼申し上げます」と「感謝申し上げます」は、どちらも丁寧な感謝の表現ですが、微妙なニュアンスの違いがあります。
「御礼申し上げます」は、どちらかというと形式的でフォーマルな場面で多く使われます。特に、ビジネスメールや挨拶状などでの使用頻度が高いです。
一方で「感謝申し上げます」は、やや感情を込めた印象を与える表現です。「深い感謝の気持ち」を強調したいときに使われることが多く、結婚報告や長年の支援への感謝状などで好まれます。
たとえば、
-
ビジネスメールでは「御礼申し上げます」
-
結婚の報告状では「感謝申し上げます」
というように使い分けると自然です。
使い分けを意識することで、より適切な敬語が使えるようになります。
「ありがとうございます」との使い分け
「ありがとうございます」は日常的に最もよく使われる感謝表現です。カジュアルな会話から、ある程度フォーマルな場面でも使える汎用性の高さがあります。
一方、「御礼申し上げます」はあくまでフォーマルな表現であり、書き言葉としての使用が多いのが特徴です。
たとえば、対面の会話やカジュアルなチャットでは:
-
「本当にありがとうございます」
とするのが自然ですが、メールや文書では:
-
「心より御礼申し上げます」
のようにすると、より丁寧な印象を与えます。
使い慣れた「ありがとうございます」だけでなく、場面に応じて適切に使い分けられるようにしましょう。
「お礼申し上げます」との違い
「御礼申し上げます」とよく似た表現に「お礼申し上げます」がありますが、実はこの2つにも微妙な差があります。
「御礼」は「お礼」よりもより丁寧な言い方で、漢字の「御」は尊敬語として相手に敬意を表します。
つまり、「お礼申し上げます」より「御礼申し上げます」の方がフォーマルで丁寧な印象になります。
ビジネス文書や社外向けのメールでは「御礼申し上げます」を使い、やや親しみを込めたい場面では「お礼申し上げます」を使うなど、バランスをとると良いでしょう。
フォーマル度による使い分け表
以下の表は、「御礼」に関する表現をフォーマル度別にまとめたものです。
| 表現 | フォーマル度 | 使用シーン |
|---|---|---|
| 御礼申し上げます | 非常に高い | 取引先、公式な文書 |
| 感謝申し上げます | 高い | 結婚・退職などの報告文 |
| お礼申し上げます | やや高い | 上司や社内メール |
| ありがとうございます | 標準 | 日常会話・軽いメール |
| 本当にありがとう | 低い | カジュアルな会話 |
このように、言葉の選び方ひとつで印象は大きく変わります。相手や場面に合わせた使い分けを心がけることが大切です。
場面ごとに変える!おすすめの言い換え集
最後に、「御礼申し上げます」の代わりに使えるおすすめの表現をいくつか紹介します。すべて敬語表現なので、置き換えて使っても失礼になりません。
| シーン | 言い換え表現 |
|---|---|
| ご挨拶 | 「心より感謝申し上げます」 |
| お詫びとセットで | 「恐縮ではございますが、御礼申し上げます」 |
| 資料提供などへのお礼 | 「早急なご対応、誠にありがとうございます」 |
| 長期的な支援に対して | 「長らくのご支援に、深く感謝申し上げます」 |
| 略式の手紙 | 「取り急ぎお礼申し上げます」 |
どの言葉もフォーマル度や印象が異なるため、覚えておくと便利です。
日本語の敬語文化を知ろう
敬語の基本3種類とは?
日本語の敬語は大きく3つに分けられます。
-
尊敬語(相手の行動を敬う)
-
謙譲語(自分の行動をへりくだる)
-
丁寧語(丁寧な言い回し)
「御礼申し上げます」は、謙譲語と丁寧語が合わさった表現です。
-
「申し上げます」:自分の行動(感謝の気持ちを伝える)をへりくだる(謙譲語)
-
「御」:丁寧語の接頭語として使われる
このように、複数の敬語が組み合わさって「御礼申し上げます」という丁寧な表現になっているのです。
謙譲語の役割と背景
謙譲語の役割は、自分をへりくだらせることで、相手を立てるという日本独特の文化に根付いています。
日本社会は「和」を重んじるため、直接的に自分の感情や意見を押しつけるのではなく、丁寧に伝えることが美徳とされています。
「御礼申し上げます」はまさにその象徴とも言える表現で、相手を尊重しながら自分の感謝の気持ちを表す方法として非常に優れています。
なぜ「申し上げます」は丁寧なのか?
「申し上げます」は「言う」の謙譲語ですが、なぜこれが特別に丁寧な印象を与えるのでしょうか?
理由は、「申し上げる」は動詞「申す」に「上げる」がついたもので、
「言葉を上に(=相手に)差し出す」というニュアンスを持っています。
このように、自分の発言や気持ちを“差し出す”という姿勢を見せることで、自然と丁寧さや誠意が伝わるのです。
日本人の礼儀と文化的背景
日本人は古くから「言葉に心を込める文化」を大切にしてきました。
例えば、茶道や武道でも「礼に始まり礼に終わる」と言われるように、形式を通じて相手を尊重する精神が根付いています。
ビジネスでも同様に、丁寧な言葉遣いは相手との信頼関係を築くための第一歩となります。
「御礼申し上げます」は、ただの言葉ではなく、日本人の文化と礼儀が詰まった表現なのです。
正しい言葉遣いが信頼を作る理由
メールや文書において、正しい敬語を使えるかどうかは、相手にとって「信頼できる人かどうか」を判断する大きなポイントになります。
「御礼申し上げます」という丁寧な表現を使いこなせるだけで、あなたの印象は確実に良くなります。
逆に、言葉遣いが雑だったり、間違った敬語を使ってしまうと、「この人はマナーを知らないのかも」と思われてしまうリスクもあります。
社会人として信頼される第一歩は、適切な言葉遣いを身につけること。
「御礼申し上げます」は、そのスタートラインに立つための基本表現とも言えるでしょう。
まとめ
「御礼申し上げます」は、ビジネスやフォーマルな場面で非常に重宝される感謝表現です。ただの「ありがとう」では伝わらない、丁寧さと誠意を表すことができます。
この記事では、「御礼申し上げます」の意味や使い方、読み方の注意点から、似た表現との違い、敬語文化に至るまで詳しく解説しました。
正しく敬語を使えることは、社会人としての信頼や評価につながります。ぜひ日常のビジネスメールや会話で、今回の内容を役立ててみてください。